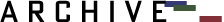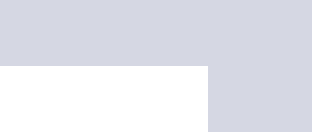
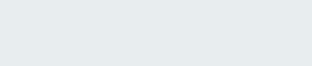


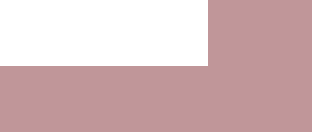
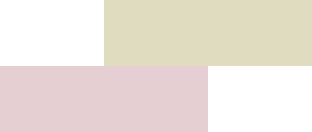
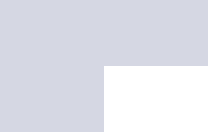


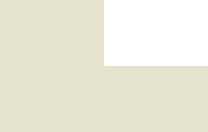
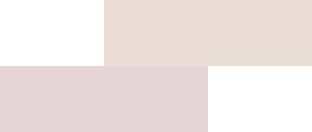

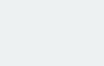

第三回アドバイザリーボード
第三回のアジェンダは、TCAとして注力する案件の方向性と個別事例の振返りについて。
データガバナンスの在り方(1)<アドバイザリーボードVol.6> の続きです。
中部電力グループにおけるデータガバナンス
- CE 内 田
- 中部電力としてグループ大のデータガバナンスを考えていますが、事業会社や部門ごとに管理責任者を置いていくのがよいのでしょうか。
- ACN保 科
-
必要です。それがないと今後コントロールが難しくなりますし、世間の目も厳しくなってくるので早めに手を打っておいた方がいいと思います。
できれば役職として置くべきですし、実際にその方が管理するのか、またはきちんと監視・コントロールできる方を下につけるのかは考えねばなりません。ただ、役割が多岐にわたることに加え、アルゴリズムに含まれる要素についてはかなりの専門性を要してしまいます。
難しい部分ではありますが、そういう方がいるといないとでは大きな差があり、取り組もうとすることが重要です。
- CE 増 田
- 先々を見据えて取り組むことはよいのですが、どの時点でどんな内容を適用するかについては、ビジネスとマッチさせる形で考える必要があります。
- ACN保 科
-
まず何が決定的要素になるのかを考えることが大切です。
絶対的に危険なデータ項目がありますので、その部分だけでもしっかりとトラップできるようにしておくだけでも違います。
私もデータを取り扱う際には、まず人のデータなのか物のデータなのか、サンプリングされているか否か、センシティブ属性を含むか、またセンシティブ属性がある場合にはそれを使用して何をしようとしているのか、ということを気にします。
- CE 内 田
- 中電グループ内でのデータ流通を促進するための管理者という観点も必要です。
- ACN保 科
- 流通が可能なデータの範囲とともに、経済効果を示していくことが必要だと思います。
- CE 増 田
- まずデータ活用には意味があるという共通のポリシーを持つ必要があります。そのうえでリスクをどのように担保するのかを考えるということだと思います。何も考えずに情報を出さないということでは、せっかくのデータを保有していても社会のために活用できません。
- ACN保 科
-
その背景には、データ活用というものがよく分からないため、怖くて出さないという考えがあると思います。
ポリシーを示すことで、流通を促進する方向に向かっていただきたいと思います。
- TCA西 浦
- 議論に上がったことを実施していく仕組みの準備や壁打ちの体制が必要だと理解しました。
- CE 内 田
- 経営戦略本部と連携しながら、データガバナンスやデータマネジメントのルール作りをしようとしているところです。
データ活用のルール整備
- CE 伊 藤
- TCAでは個人情報を含むデータは扱っているのでしょうか。
- TCA野 田
-
一部は取り扱っております。ただ、我々がデータを保有しているわけではありません。
グループ内では会社によっては保有しているところもあるものの、細目に渡ってデータガバナンスの話ができているわけではないというのが現状かと思います。
- CE 伊 藤
- 契約に記載していくということではないでしょうか。
- TCA西 浦
- 実証という形にしてしまうと検証用と言いながら何でも共有できてしまう懸念もあります。
- TCA野 田
- まだサービスに対してそれほど多くのユーザーがついていないにもかかわらず、システム連携により大量のデータを連携しようとしている事例もあります。
- CE 伊 藤
-
私は系統解析を長くやっていました。
系統解析には機微なデータがありますが、過去にはメーカーなどに委託を出し、共同研究で分析していました。
あるタイミングで、それまで暗黙の了解としていた二次流通の規制や委託期間終了後の破棄といった内容を、契約に明記するようになりました。
しかしながら、契約先の企業まで完全にコントロールするのは難しいのではないかという気もします。
- CE 増 田
- むやみにデータを授受するのではなく、まず提供するサービスを検討して、マッチするデータのみを授受するようにしなければなりません。
- TCA野 田
-
一概に使ってはいけないというものではないため、うまくルール作りをしていかねばなりません。
規約やルールの範囲内で使用することは問題ないですが、それが外部には絶対に漏れないことが必要不可欠です。
- TCA栗 林
- ゆくゆくは、グループ全体でのガバナンスやルールが定まることが望ましいです。それまでの間は、グループ内でも事業会社間で契約として根拠を残していくことも必要かもしれません。その活用事例をガバナンスやルールに反映させるという考え方もあります。
- TCA野 田
-
大事なテーマですので、引き続き整理を進めていただきたいです。
恐らくここにもリテラシーの問題があり、データの取扱いにかかる重要性をあまり気にしていない人もいるのではないでしょうか。リテラシーを上げると一言で言っても、さまざまな項目があると思いますし、その向上にTCAとしてもお手伝いできればと思います。
- ACN保 科
-
医学系の研究に多く携わっているので、そこでは多くの個人情報データを取り扱います。データをそのままの状態でいただくことはあまりなく、どのような分析モデルを作りたいかによって必要なデータのみを使って中間表現データを作り、それを共有する形をとっています。
全てのケースに適用できるわけではないですが、仕組みを作ることでも大きな違いがあると思います。そういった仕組みについても必要に応じて今後共有させていただきます。
第三回アドバイザリーボード