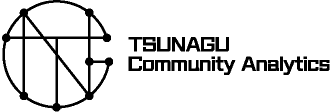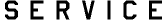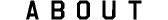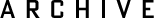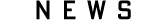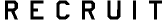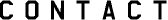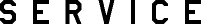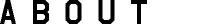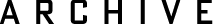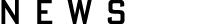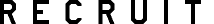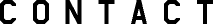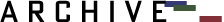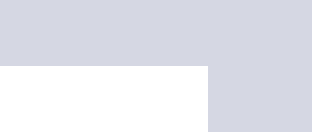
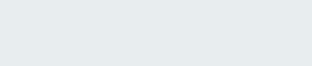


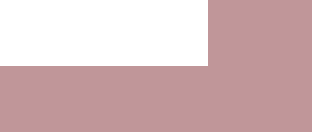
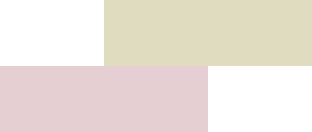
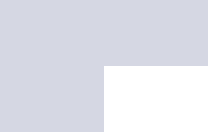


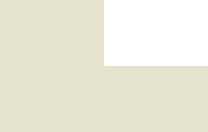
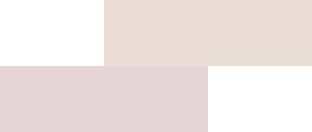

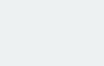
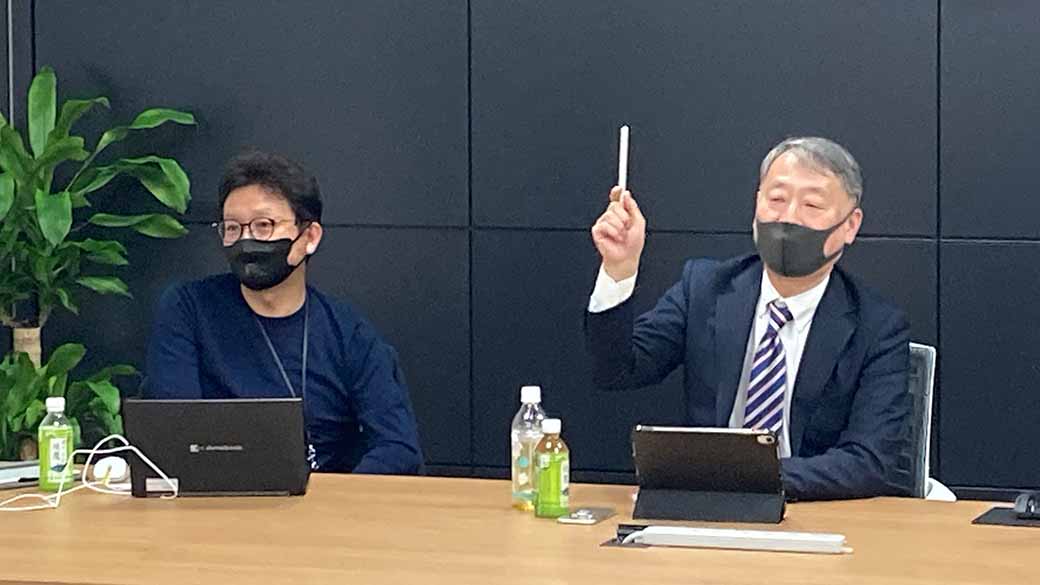
第三回アドバイザリーボード
第三回のアジェンダは、TCAとして注力する案件の方向性と個別事例の振返りについて。
今後の注力する案件の方向性<アドバイザリーボードVol.1> の続きです。
実施案件から見える課題と学び
- TCA西 浦
-
それでは次のテーマとして、TCAが21年度に取り組んだ案件の中から、主だった4つの課題を紹介し、ディスカッションを行いたいと思います。これらは、一般的によく見受けられるものでもあります。
課題Aは、不十分な目的の定義。
課題Bは、複数部署間での取り組み優先度の調整。
課題Cは、目的に応じたツール導入の必要性。
事例Dは、PoC(概念実証)段階での業務適用。
また、最後に、データのマネジメントついても取り上げたいと思います。
ここから夫々の事例を紹介します。
課題A 不十分な目的の定義
- TCA西 浦
-
まず、課題Aになります。
IoT機器の導入によりビッグデータの活用が可能になり、それを使った既存ビジネスの高度化や新規ビジネスの創出ができないかについてアイディアベースで考えることはよくあると思います。
このようなことが実現可能かもしれないというアイディアを持つことはとても重要です。しかし案件の目的・ゴールが不透明だとどのような分析モデルを構築する必要があるか、どこまで精度を上げる必要があるかが決まりません。
そのため、既存ビジネス高度化の案件に於いては、現行の制度や業務の内容を確認しながら、まず取り組むべき課題・影響範囲・効果を出すポイント等の上流を整理するプロセスが必要となります。その上で、どのような分析モデルを構築するのかを集約します。
業務変革を推進していく際には理想像の発想に加え、実行時の影響範囲を総合的に判断し最大限の成果を創出できる方式や順序を考慮することが重要です。それによって、1つの取り組みの効果を何倍にも活かすことができると思います。
課題B 複数部署間での取り組み優先度の調整
- TCA西 浦
-
課題Bは、複数部署間での取り組み優先度の調整です。
複数の部署が絡む案件では、目的や案件実施のスピード感が合わないことがあります。
このような場合には、グループ全体の視点を持ちつつ事業会社や事業部において何を優先して取り組んでいくべきかという順序付けについて意識統一が必要となります。
多くの方々がデータ活用や業務改善に対する思いを持つがゆえに事業部間の調整が難航することもあります。
グループ全体最適の視点を踏まえつつ、誰と何を進めるか、事業部内において誰と調整を行うのかについて、もう少し意識しながら進めねばならないというのが教訓です。
各社の意識のすれ違いにも課題
- TCA野 田
- TCAで議論していた内容としては、場合によっては各事業会社や部門間での利益相反もあり得るということです。グループ全体としての目的や方向性を考慮する必要があります。
- CE 伊 藤
-
同感です。
分社化の結果として、それぞれが自律的な経営の結果として部分最適を求めにいってしまう傾向がある部分もあり、それがTCAとしても疑問に感じている部分かと思います。経営戦略本部でも、このような課題については毎日議論しています。
第三回アドバイザリーボード